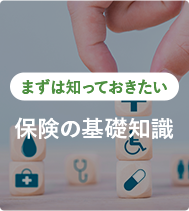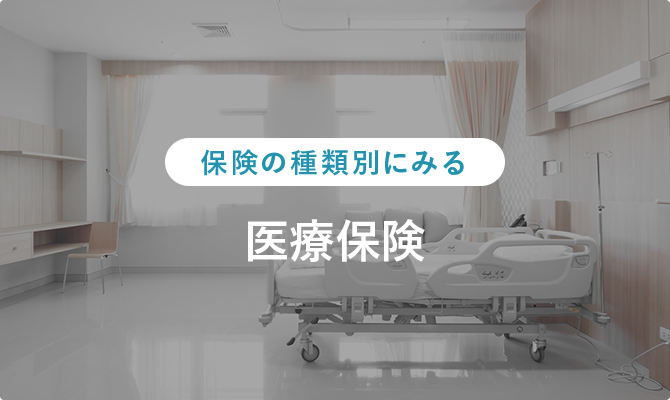認知症
【これから介護を始める方】
家族が認知症になってしまった際の対応
この記事では認知症の基礎知識や、認知症患者への基本的な対応、症状別の接し方、家族が心得ておくべきことについて解説します。
[注1]厚生労働省 知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス総合サイト「認知症」
目次
- <基礎知識>認知症にはどんな症状があるの?
- 認知症患者への基本的な対応
- 認知症が引き起こす症状別の接し方
- 家族が心得ておくべき認知症介護。介護に疲れないために 1.ひとりで抱え込みすぎない 2.外部サービスを検討する 3.否定せず、行動の背景にある理由を考える 4.周囲と比べない
- まとめ
<基礎知識>認知症にはどんな症状があるの?
認知症とは、加齢にともなう病気の一種です。[注2]
さまざまな原因によって脳の細胞が死滅、または機能が低下することによって、記憶力や判断力などに障害が起こり、日常生活に支障をきたすようになります。
加齢による物忘れと混同されがちですが、認知症による物忘れは体験したことそのものを忘れる、物忘れの自覚がないといった特徴が見られます。
主な症状としては、中核症状と行動・心理症状の2種類があります。
中核症状は、物忘れ(記憶障害)、時間・場所がわからなくなる、理解力・判断力の低下、身の回りのことができなくなる、などといった症状が挙げられます。
一方、行動・心理症状は、ひとりになると不安を感じる、趣味や好きなことに興味を示さなくなる、自分のものを盗まれたと疑う、外出先から帰宅できなくなる、などの症状があります。
また、認知症の疾患は、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症など複数の種類に分類されます。
認知症の概要や種類について、詳しくは「認知症の種類とそれぞれの原因・症状を解説」をご覧ください。
[注2]政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
認知症患者への基本的な対応

認知症になると、物忘れや理解・判断力の低下などにより、徐々に日常生活に支障をきたすようになります。
本人はもちろん、身近にいる家族も、これまで通りの生活を送るのが難しくなり、戸惑いを感じることも多いでしょう。
現代医学では認知症に対する有効な治療法は確立されていませんが、日々の生活の中で適切な対応・処置を行えば、進行を緩やかにすることが可能と言われています。
「もしも」の場合に備え、認知症になった家族への対応方法を覚えておきましょう。
ここでは認知症患者への基本的な対応についてをご紹介します。
まずは様子を見守る
認知症の初期症状は、加齢による物忘れと判断がつきにくい傾向にあります。
物忘れが増えたり、理解力や判断力の低下が見られたりしても、すぐに「認知症」と断定せず、まずは様子を見守ってみましょう。
普段の様子をさりげなくチェックし、加齢による物忘れではなさそうだと判断したら、医療機関や地域包括支援センターなどの然るべき施設に相談することが大切です。
声かけはなるべくひとりで行う
認知症の初期症状は本人も自覚があるため、「もしかしたら認知症ではないか」と大きな不安を抱えています。
恐れと不安を抱いている相手に、複数人で声をかけると、パニックに陥ってしまうおそれがあります。
物忘れなどの兆候が見られるようになったら、家族のうちのひとりが代表して声をかけ、むやみに刺激を与えないよう注意しましょう。
また、話しかけるときは相手の目線に合わせ、なるべく優しい口調で、はっきりと話すことを心がけるのがポイントです。
なるべく明るい気持ちになってもらうようサポートする
認知症かもしれないと自覚することは、本人に大きな衝撃をもたらします。
人によっては塞ぎ込んでしまい、物忘れなどの症状と重なって生活に支障をきたすおそれがあります。
身近にいるご家族にとってもショックの大きい出来事ですが、普段の生活では自然にふるまい、できるだけ明るい気持ちになってもらえるよう配慮しましょう。
たとえば、最近あった明るい出来事を話題にする、写真を見ながら楽しい思い出について語り合うなどです。
心の中の不安を吐露するだけで気持ちが楽になることもありますので、相手の言葉にじっくり耳を傾け、その気持ちを受け止める姿勢を持つといった対応も大切です。
叱る、命令する、強制するなどの行動はNG
認知症になると、記憶力や理解力、判断力の低下が見られるため、以前よりも行動が遅れがちになります。
その様子を見ると、つい「なぜこんなこともできないの」「もっと早くして!」とイライラしてしまいがちですが、激しく叱ったり、責めたりすると、相手が心を閉ざす原因となります。
場合によっては認知症の症状がさらに進行してしまう可能性もありますので、自尊心を傷付けるような行動は控えましょう。
認知症が引き起こす症状別の接し方
認知症になると、理解力や判断力、記憶力といった認知機能の低下により、発症前には見られなかった行動が出てくることもあります。
時には家族が対応に困るような言動をすることがあるため、どのように対応したらよいか悩んでいる方も少なくありません。
以下では、認知症が引き起こす言動に対する基本的な接し方を症状別にまとめました。
接し方に対する反応には個人差があるため、すべての方に適した方法とは言えませんが、一例として参考にしてみてください。
被害妄想への接し方
認知症になると、自分のものを他人に盗られたと思い込む「もの盗られ妄想」が起こりやすくなります。
その場合、身近にいる人間が真っ先に疑われますが、怒ったり否定したりすると、かえって興奮して逆効果になりかねません。
話をよく聞いて、盗られたと思っていることに「大変ですね」などと共感し寄り添い、一緒に探して本人に見つけさせるように仕向けるなど、穏便に解決できる方法を模索しましょう。
暴力的な行動への接し方
暴言を吐かれたり、叩く・突き飛ばすといった暴力的な行動を取られたりした場合は、とにかく相手の気持ちを落ち着かせることを優先しましょう。
ひどい言葉をぶつけられると悲しい気持ちになりますが、言い返したり、力尽くで抑えたりするとますます激昂する可能性もあるので「落ち着いてほしい」「何に怒っているのか聞かせて」などと声をかけ、気持ちを少しでも鎮静化させることが大切です。
行方不明になった場合の対応
認知症になると記憶力が低下するため、外出先から帰宅できなくなる場合があります。
外出させまいと、靴を隠したり、部屋の外側から鍵をかけたりすると、室内で暴れたり窓から脱走しようとしたりするおそれがありますので、過度な行動制限はNGです。
24時間家族が見張っているのも難しいので、もしもの場合を考慮し、名前や連絡先を記載したタグなどを身につけさせるなどの工夫をとり入れましょう。
ご近所の方に事情を話し、うろうろしているのを見かけたら報せてほしいと協力を仰ぐのもひとつの方法です。
失禁への対処法
トイレを失敗するのは本人にとっても大きな衝撃で、ひどく自尊心が傷つけられます。
そこに追い打ちをかけるように叱ったり、責めたりするとトイレの失敗を隠すようになりますので、本人の自尊心を傷つけないよう、さりげなく片付けることを心がけましょう。
排泄を失敗する前に、定期的にトイレに行くよう声をかけたり、トイレの前に「トイレ」と大きな貼り紙をつけたりすると、トイレの失敗予防に役立ちます。
家族が心得ておくべき認知症介護。介護に疲れないために

認知症の方の介護は心身に大きな負担をもたらすため、時として介護する側の日常生活に支障をきたす原因となります。
身内の介護を行うようになったら、介護疲れが深刻化しないよう、自身の心や身体の負担を軽減する工夫を採り入れることが大切です。
ここでは認知症介護を行う家族が心得ておくべきことを4つご紹介します。
1.ひとりで抱え込みすぎない
認知症の介護は非常に大変なことなので、ひとりだけで抱え込もうとすると早々にダウンしてしまうおそれがあります。
他の家族や親族に相談するのはもちろん、医師や看護師、ケアマネジャーなど、積極的に専門家の助けを借りることも検討しましょう。
2.外部サービスを検討する
介護する側にも自分の生活がありますので、たとえ交代制でも家族だけで介護のすべてを切り盛りするのは困難です。
現在は公的・民間含めてさまざまな介護支援サービスが提供されていますので、上手に活用して家族の負担を減らしましょう。
65歳以上の人は要介護状態や要支援状態と認定されれば、介護保険の適用により、介護支援サービスの費用負担を軽減できます。[注3]
[注3]厚生労働省「介護保険制度の概要」p5
3.否定せず、行動の背景にある理由を考える
認知症の方は、周囲から見ると突飛な言動を取りがちですが、そこには当人なりの理由や背景が存在します。
頭から否定したりせず、なぜこういう行動を取るのか、どんな背景があってこうした言葉を発するのか、冷静に分析してみましょう。
ある程度、理由や背景がわかってくれば、適切な対応の仕方も判断しやすくなります。
4.周囲と比べない
認知症の進行度には個人差があり、緩やかに進行する方もいれば、急速に症状が悪化する方もいます。
他の事例と比べて一喜一憂するのはあまり意味がなく、むしろ本人や介護する家族を追い詰める原因となる場合が多いので、比較はしない方が賢明です。
まとめ
認知症になるリスクは年齢を重ねるほど高くなると言われています。
一方で、認知症になる要因は年齢だけに限らず、中には65歳未満で「若年性認知症」になる方もいます。
このように、認知症は誰でもなり得る可能性のある症状ですので、認知症に対する正しい理解を深めると共に、早期治療に備えることが大切です。
スマ保険では、所定の認知症に一時金で備えることができる「ひまわり認知症予防保険」を取り扱いしていますので、ぜひご検討ください。