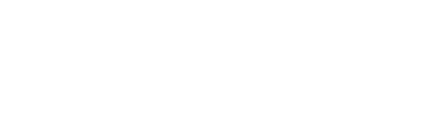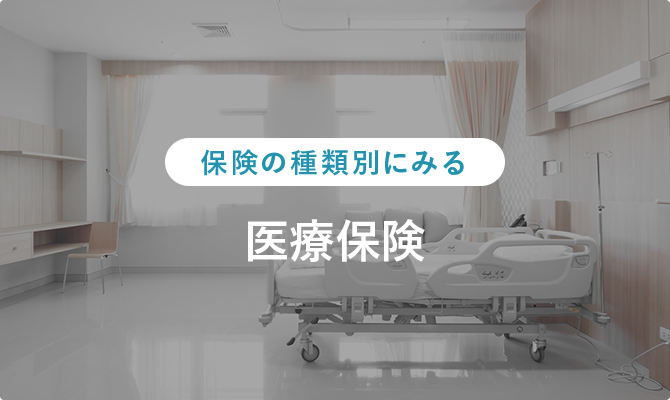基礎知識
個人年金保険は年末調整で控除される?
適用条件や手続き方法など徹底解説
この記事では、個人年金保険に加入することで得られる税負担軽減のメリットや、具体的な手続き方法などを解説します。
この記事を読んでいる方は
以下の商品も閲覧しています
閉じる
個人年金保険は年末調整や確定申告での控除対象
個人年金保険に加入して保険料を払い込むと、生命保険料控除として、年末調整や確定申告時に控除されます。控除とは、所得から差し引くもので、控除額が大きくなればなるほど納める所得税と住民税は安くなります。
生命保険料控除には「生命保険契約等」「介護医療保険契約等」「個人年金保険契約等」があり、個人年金保険は「個人年金保険契約等」が受けられ、控除を受けるためには下記の条件を満たさなければなりません。[注1]
- 年金受取人が契約者か、またはその配偶者であること
- 年金受取人が被保険者と同一人であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから払い込むとされている10年以上の定期または終身の年金であること
たとえば、年金受取人が契約者の親である場合や、保険料の払込期間が10年未満の場合は個人年金保険料控除を受けられません。すべての個人年金保険の契約で、控除が適用されるわけではない点に注意しましょう。
なお、当社で個人年金保険料控除が適用されるためには、個人年金保険料税制適格特約を付加する必要があります。
[注1]国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
個人年金保険料控除の適用限度額は?
個人年金保険料控除は、適用される金額に上限が設けられています。払い込んだ保険料の全額が、控除の対象となるわけではない点に留意しましょう。
なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約を「新契約」、平成23年12月31日以前に締結した保険契約を「旧契約」と呼びます。新契約と旧契約では、控除できる金額が異なります。[注2]
<新契約の個人年金保険料控除額(所得税)>
| 年間の払込保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 払込保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 払込保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
<旧契約の個人年金保険料控除額(所得税)>
| 年間の払込保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 25,000円超50,000円以下 | 払込保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下 | 払込保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
<新契約と旧契約の両保険に加入している場合の個人年金保険料控除額(所得税)>
| 年間の払込保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 旧個人年金保険料控除の年間払込保険料等の金額が60,000円を超える場合 | 旧契約と同じ計算方法(最高50,000円) |
| 旧個人年金保険料控除の年間払込保険料等の金額が60,000円以下の場合 | 新契約の個人年金保険料は新契約と同じ計算式、旧契約の個人年金保険料は旧契約と同じ計算式で算出した額の合計(最高40,000円) |
また、住民税に関しても控除を受けられますが、計算方法や控除の上限額が所得税とは異なります。[注3]
<新契約の個人年金保険料控除額(住民税)>
| 年間の払込保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | (払込保険料等×1/2)+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | (払込保険料等×1/4)+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
<旧契約の個人年金保険料控除額(住民税)>
| 年間の払込保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | (払込保険料等×1/2)+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | (払込保険料等×1/4)+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約について保険料を払い込んでいる場合、新契約と旧契約で計算し、合計した額(上限28,000円)が控除額になります。
[注2]国税庁「No.1140 生命保険料控除」
[注3]公益財団法人生命保険文化センター「生命保険と税金」
※2023年11月現在の税制に基づいた記載であり、税務の取扱については税制改正などで将来変更となることがあります。個別の取扱等については、所轄の税務署等にご確認ください。
個人年金保険料控除の手続き方法

個人年金保険料控除を受けるためには、所定の手続きを行う必要があります。
会社員や公務員の場合、年末調整の時期になると勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」が渡されます。契約している保険会社名や払い込んだ保険料、保険料に応じた控除額を記載しましょう。
また、年末調整の時期になると保険会社から「生命保険料控除証明書」などのハガキが届きます。保険料控除申告書と保険料払込証明書を勤務先に提出すれば、一連の手続きは完了です。
自営業・フリーランスの方などで年末調整が行われない場合は、自身で確定申告を行う必要があります。確定申告書の第二表に「新個人年金保険料の計」と「旧個人年金保険料の計」という欄があるので、該当する欄に払い込んだ保険料を記載しましょう。
あわせて保険会社から送られる生命保険料控除証明書も添付する必要があるため、確定申告時に忘れずに添付しましょう。
いずれの場合でも、書類に不備があると控除が受けられないため、書類漏れがないようにきちんと提出することが大切です。
個人年金保険に加入したら必ず年末調整・確定申告時に控除の申請をしよう
個人年金保険料控除の適用を受けることで、所得税と住民税の負担を抑えることができます。公的年金の上乗せとなる老後資金を工面しつつ、税負担の軽減も同時に行える点は資産形成上メリットと言えるでしょう。
軽減できる税金額は年間数千円〜数万円程度になり、中長期的に加入すれば税負担を大きく抑えられるでしょう。
<個人年金保険の加入により軽減できる税金額(新契約の場合)>
| 軽減できる所得税(上限) | 軽減できる住民税(上限) | 合計(上限) | |
|---|---|---|---|
| 所得税率5%の人 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 |
| 所得税率10%の人 | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 |
| 所得税率20%の人 | 8,000円 | 2,800円 | 10,800円 |
せっかく個人年金保険に加入しても、控除を受けられなければ加入するメリットが薄れてしまいます。個人年金保険に加入した後は、必ず所定の手続きを行い、控除を受けるようにしましょう。
この記事を読んでいる方は
以下の商品も閲覧しています
ネットで加入できる!太陽生命の「個人年金保険」

太陽生命ダイレクト「スマ保険」では、ネットで手軽に加入できる利便性に優れた個人年金保険を取り扱っています。太陽生命ダイレクト「スマ保険」の「個人年金保険」は、月々5,000円から加入できるため、家計の負担を抑えながら老後に向けた資産形成を行えます。
老後のライフスタイルに合わせて、受け取り方法を「年金受取」か「一括受取」から選択できます。
もし、被保険者が年金を受け取る前に死亡した場合でも死亡給付金が払い込まれるため、万一の備えとしても活用できるでしょう。
個人年金保険の契約を検討している方は太陽生命ダイレクト「スマ保険」で検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
個人年金保険を活用すれば、老後に向けて資産形成を行いながら、税金額を軽減することができます。中長期的に個人年金保険に加入すれば、税負担を抑えられる金額の総計も大きくなるでしょう。老後に何らかの不安を抱えている方にとって、個人年金保険は不安を軽減する有用な手段となります。
ただし、個人年金保険で控除を受けるためには、年末調整や確定申告などの手続きをする必要があります。個人年金保険に加入した後は、必要書類を漏れなく提出することを忘れないようにしてください。
なお、個人年金保険料控除が適用されるには、個人年金保険料税制適格特約を付加する必要があります。詳細については各保険会社の約款等をご覧ください。
太陽生命ダイレクト「スマ保険」の「個人年金保険」は、月々5,000円から始めることができます。家計の保険料負担を抑えながら老後に向けた資産形成ができるため、個人年金保険を探している方は加入を検討してみてはいかがでしょうか。