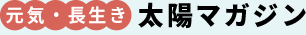ワンオペ育児とは?子育ての負担を上手に乗り越える方法
現代日本が抱える社会問題の一つ、ワンオペ育児とはどのような状況を指すのでしょうか。
ワンオペ育児は当事者の心身に大きな負担がかかります。これから育児を始める予定がある人も、すでに育児中の人も、その実態や乗り越えるコツについて学んでおきましょう。
この記事では、ワンオペ育児とはどのようなものなのか、現代日本における実態やワンオペ育児になる理由を紹介するとともに、ワンオペ育児を乗り越えるコツについて解説します。

ワンオペ育児とは?
ワンオペ育児とは、「ワンオペレーション育児」の略称です。
語源となるワンオペレーションは、もともと飲食店やコンビニなどの営業を従業員一人でまかなうことを意味する言葉です。
そこから、両親のどちらか一方、またはひとり親が家事・育児のほとんどを一人で行うことを「ワンオペ育児」と呼ぶようになりました。
なお、ワンオペ育児とは近年新しく生まれた造語であり、今では世間一般に浸透しています。
他の先進国に比べて日本では、母親がワンオペ育児状態に陥るケースが多い傾向にあります。
ワンオペ育児の実態

ワンオペ育児とはどのような状況を指すのか、概要を説明しました。
また、日本では母親がワンオペ状態になるケースが多くなっており、その実態は統計でも明らかになっています。
総務省がまとめた「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果」によると、直近20年での6歳未満の子を持つ世帯における夫婦別の家事関連時間(時間.分)は以下のようになっています。[注1]
| 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家事関連 | 0.48 | 1.00 | 1.07 | 1.23 | 1.54 |
| 家事 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.30 |
| 介護・看護 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 育児 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 1.05 |
| 買い物 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家事関連 | 7.41 | 7.27 | 7.41 | 7.34 | 7.28 |
| 家事 | 3.53 | 3.35 | 3.35 | 3.07 | 2.58 |
| 介護・看護 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 育児 | 3.03 | 3.09 | 3.22 | 3.45 | 3.54 |
| 買い物 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.33 |
近年は女性の社会進出が当たり前の時代になり、20年前に比べると家事関連時間の夫妻差は徐々に狭まりつつあります。
しかし、直近の2021年のデータでもなお、妻が家事関連に費やす時間は夫の約4倍と長く、依然として夫妻差は大きいままです。
育児に費やす時間についても、夫は約1時間であるのに対し、妻はその4倍にあたる約4時間となっており、母親のワンオペ育児が顕著であることがうかがえます。
厚生労働省がまとめた資料によると、2010〜2014年は第一子出産後でも約4割の女性が仕事を継続しており、1980年代に比べると共働き世帯は約1.5倍に増加しています。[注2][注3]
しかし、育児を含む家事関連時間の夫妻差は20年経っても大きく縮まっておらず、共働き世帯であっても母親のワンオペ育児率が高い実態が浮き彫りになっています。
[注1]総務省「令和3年社会生活基本調査生活時間及び生活行動に関する結果」 p5
[注2]厚生労働省「令和4年厚生労働白書」 p182
[注3]厚生労働省「図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移」
ワンオペ育児になる理由
日本でワンオペ育児率が高い理由は、大きく分けて5つあります。
1. パートナーが単身赴任している
パートナーが仕事の関係で単身赴任していると、必然的にワンオペ育児にならざるを得ません。
単身赴任先によっては、1〜2ヶ月に数回しか帰宅できないというケースも多く、平日はもちろん、休日もワンオペ育児を強いられることがあります。
単身赴任先についていくという方法もありますが、自身の異動希望や転職が難しい、就学している上の子がいる、持ち家である、会社が用意した赴任先の住居がワンルームだったなど、さまざまな理由で引っ越しが難しいケースも多いようです。
2. パートナーの仕事が多忙で家にいる時間が少ない
単身赴任ではないものの、パートナーの仕事が多忙で、早朝から遅くまで仕事をしている場合もワンオペ育児になりやすい傾向にあります。
仕事で不在のときはもちろん、帰宅してからも疲れ果てているパートナーに家事や育児を任せるのを躊躇してしまう人も多いようです。
3. シングルマザー/シングルファザーである
シングルの人は、育児や家事を分担できるパートナーがいないので、ワンオペ育児になります。
しかも、シングルの人のほとんどは家計を支えるために働いているため、家事や育児に加えて仕事もしなければならず、心身の負担はより大きくなりやすいでしょう。
4. 実家が遠く、すぐに頼れる人が近くにいない
かつての日本は、三世代で同居する世帯も多く、両親の手が回らないときは祖父母が代わりに家事や子育てを担うのが一般的でした。
しかし、核家族化が進んだ現代では、実家から遠く離れた場所で家族を持つケースも多く、何かあっても近場に頼れる人がいないという夫婦は珍しくありません。
出産のために一時的に里帰りする母親もいるものの、年単位で続く育児の場合、長期的に実家へ身を寄せるのは難しく、最終的に一人ですべてを背負わざるを得ない状況へと追い込まれがちです。
5. パートナーが子育てに非協力的
諸外国に比べて日本では、いまだに「家事・育児は女性が担うもの」という考えの人が一定数います。
特に専業主婦の場合、「働いていない人が家事・育児をやるのは当たり前」と男性側だけでなく女性本人も考えている人が意外と多く、休日でも母親がワンオペ育児をしているケースが多々見受けられます。
ワンオペ育児を乗り越えるコツ

ワンオペ育児を乗り越えるために、押さえておきたいコツを5つご紹介します。
1. 完璧を目指さない
一人の人間ができることには限界がありますので、家事・育児のすべてに完璧を求めようとすると心身に不調をきたす原因になります。
家事・育児に対する理想があったとしても、決して無理はせず、「ほどほどでいい」「まあいいか」と気楽に考えることも一つの方法です。
食洗機やお掃除ロボット、自動調理器などの便利家電を積極的に活用すれば、家事の負担を軽減することができます。
2. 周囲に協力を求める
子育て中は、ただ忙しいというだけでなく、不安や悩み事も抱えやすい時期です。
最も身近なパートナーに相談するのが一番ですが、単身赴任だったり、多忙だったりして、なかなか話しにくいという人も多いでしょう。
そんなときは、両親に相談したり、ファミリーサポートや一時預かりといった外部サポートを利用したりすることも検討しましょう。
周囲に助けを求めることは決して恥ずかしいことではありませんので、一人で抱え込まず、周囲に協力を求めましょう。
3. 子育ての悩みを相談できる友人を作る
相談相手が身内だと、距離が近すぎるぶん、意見の食い違いなどで衝突してしまうことも少なくありません。
身内だからこそ相談しにくい悩みや不安がある場合は、育児コミュニティや育児サークルなどに参加して、同じ境遇にいる友人を作ってみましょう。
先輩ママからためになる話を聞けるかもしれませんし、たとえ具体的な解決策が見つからなくても、不安や悩みを共有するだけで心が楽になる人もいます。
4. 役割分担する
家事や育児は本来、夫婦で分担して行うものです。
「手の空いた方がやる」といった曖昧なルールだと、どちらか一方に負担が偏ってしまいやすいので、あらかじめ役割分担を決めておくことをおすすめします。
5. 息抜きをする
いくら我が子がかわいくても、四六時中、育児にかかりきりになっていると息が詰まってしまいます。
たまにはパートナーや両親に子どもを預けたり、一時預かりなどを利用したりして自分の時間を確保し、趣味やお出かけを楽しんで息抜きしましょう。
まとめ
ワンオペ育児とは、夫婦のどちらか、またはシングルの人が家事・育児を一人でこなす状態のことです。
日本ではワンオペ育児率が高く、特に母親が家事・育児のほとんどを担うケースが多々見られます。
ワンオペ育児になってしまう理由は人それぞれですが、条件に関係なく、一人で家事・育児のすべてをこなそうとすると心身ともに疲れ切ってしまいます。
子育て中は完璧を求めようとせず、パートナーや両親、外部サービスに協力を求めながら、悩みや不安を乗り越えていきましょう。