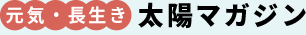早産とは?早産になる前に知っておきたい原因や兆候について
妊娠中はさまざまなリスクが生じますが、そのうちのひとつが「早産」です。
早産は赤ちゃんの生存率や予後に大きく影響すると言われており、主な原因や兆候について事前に正しい知識を得ておくことが大切です。
この記事では、早産の概要や主な原因と兆候、早産で生じるリスクについてわかりやすく解説します。

早産とは
早産とは、正期産よりも前に出産に至ってしまうことです。
正期産は妊娠37週〜42週未満での出産と定義されているため、妊娠37週未満での出産は「早産」となります。[注1]
ただし、妊娠22週未満のときに何らかの原因で妊娠が終了した場合は「流産」となるため、早産に該当するのは妊娠22週以降37週未満での出産に限定されます。[注2]
なお、早産のうち、妊娠週数34週〜37週未満で出産した場合は「後期早産」と呼ばれています。[注1]
早産の割合は全妊産婦のおよそ5%となっています。[注3]早産は原因によって「人工早産」と「自然早産」の2種類に区分されます。
人工早産とは、妊娠中に何らかのトラブルが発生し、母体や胎児に危険が及んだ場合に、人為的に早産させることです。
たとえば、妊娠高血圧症候群や前置胎盤、常位胎盤早期剥離、胎児機能不全などが原因で妊娠を継続させるのが困難と判断された場合、やむを得ず人工早産を選択することがあります。
このような人工早産以外の早産は、すべて自然早産となります。
[注1]厚生労働省「低出生体重児保健指導マニュアル」
[注2]厚生労働省「母性健康管理ガイドブック」
[注3]厚生労働省「妊産婦の診療の現状と課題」
切迫早産とは
早産に似た言葉として、切迫早産があります。切迫早産とは、早産になる危険性が高いと考えられる状態のことです。[注2]
切迫早産の症状として、規則的かつ頻繁に子宮の収縮が起こるようになり、子宮口が開いて赤ちゃんが出てきそうな状態になります。
適切な対処を行えば、開いていた子宮口が閉じて、元通り妊娠を継続させることが可能です。
一方、そのまま放置すると早産になってしまう可能性が高くなるため、切迫早産と診断されたら医師の指示に従って適切な対応・処置を行う必要があります。
早産の原因と兆候

早産のリスクが高くなる原因は複数あります。
また、早産になりかかっている時は、体に何らかの変化が生じる場合が多いので、兆候を見逃さないようにしましょう。
早産のリスクが高くなる原因
早産のリスクが高くなる主な原因には以下のようなものがあります。
妊娠中の母体の病気
妊娠中に、絨毛膜羊膜炎などの感染症にかかったり、妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離、子宮頸管無力症、前置胎盤といった病気に罹患したりすると、母体と胎児の状況を鑑み、人工早産を選ばざるを得ないことがあります。[注1]
双胎、多胎妊娠
双子の妊娠、または三つ子以上の多胎妊娠の場合、早産になるリスクが高くなると言われています。[注1]
羊水過多症・羊水過少症
羊水とは、お腹の赤ちゃんを守る役割を果たす大切な液体のことです。
羊水の量には個人差がありますが、標準より極端に多いまたは少ない場合、早産リスクが高くなると言われています。[注1]
生活習慣の乱れ
妊娠中に喫煙していると、早産のリスクが増加するという研究結果が報告されています。[注1]
また、無理なダイエットによる栄養不足は、胎児の発育不全などの要因となり、早産リスクが高くなるおそれがあります。
早産の経験がある
これまでの妊娠で早産になった経験のある方は、通常よりも早産のリスクが高くなりやすい傾向にあります。
実際に早産にならなかった場合でも、切迫早産になった経験があるのなら、通常よりもリスクが高いと考えておいた方がよいでしょう。
早産の兆候
早産しかかっている(切迫早産)状態になると、以下のような兆候が見られることがあります。[注2]
●性器からの出血
●下腹部の痛み
●下腹部の張り
●破水感
●自覚できる胎動の減少
下腹部の張りについては、妊娠後期になると正常でも頻繁に起こることがあります。
ただし、張りが周期的または持続するもので、かつ安静にしても治らない場合は切迫早産のサインである可能性が高いので、かかりつけの医師に相談しましょう。
早産のリスク

もし、早産になった場合、お腹の赤ちゃんに対してさまざまなリスクが想定されます。
ここでは、早産になった際の赤ちゃんへのリスクや、母体への影響について解説します。
赤ちゃんへのリスク
早産になった場合に想定される赤ちゃんへのリスクは、大きく分けて2つあります。
生存率が低くなる
赤ちゃんの生存率は、母体にいる期間が短いほど低くなる傾向にあります。
周産期母子医療センターネットワークデータベースに登録された在胎32週未満の赤ちゃんの生存率は以下のようになっています。[注1]
| 在胎週数 | 死亡率 | 生存率 |
|---|---|---|
| 22〜23週 | 33.9% | 66.1% |
| 24〜25週 | 13.5% | 86.5% |
| 26〜27週 | 6.0% | 94.0% |
| 28〜29週 | 3.3% | 96.7% |
| 30〜31週 | 2.5% | 97.5% |
在胎週数が22〜23週の場合、赤ちゃんが亡くなってしまう割合が約3割と高くなっています。
一方、在胎週数が26週を超えると、生存率も9割を超えるため、なるべく長く赤ちゃんをお腹の中に留めておくことが大切です。
母体へのリスク
早産における母体へのリスクは、通常の出産とほとんど変わりないと言われています。
強いて言うなら、通常より陣痛が早く来るところですが、赤ちゃんに比べて早産になることそのもののリスクは少ないと言えます。
まとめ
早産とは、妊娠22週以降37週未満で出産することで、全妊産婦のおよそ5%の割合で起こります。
感染症や妊娠高血圧症候群といった病気にかかった場合は、人為的に早産せざるを得なくなることもあります。
また、双子や多胎妊娠、羊水過多・過少症の場合などは早産のリスクが高くなると言われています。
早産になりかけている際は、出血や下腹部の痛み、周期的または持続的なお腹の張りなどの兆候が見られますので、普段から自分の体の状態をチェックし、気になる症状が現れたらかかりつけの医師に相談しましょう。
お腹の張りに関しては早産の兆候ではなくても発生することがありますが、無理をすると体に負担がかかりますので、できるだけ安静に過ごすよう心がけることが大切です。
また、早産のリスクを低減するために、禁煙や、無理なダイエットをしないなど、生活習慣の見直しにも積極的に取り組むことをおすすめします。