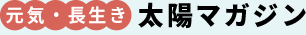糖尿病ってどんな症状?初期症状や合併症などについて知ろう
生活習慣が関わる症状の代表的な例として挙げられるのが糖尿病です。
年齢が上がるにつれて発症する可能性が高くなっていき、さまざまな合併症を引き起こす可能性があるため、糖尿病の症状や原因、合併症について事前に知り、対策をしておきましょう。
この記事では、糖尿病の症状や引き起こされる合併症について解説します。
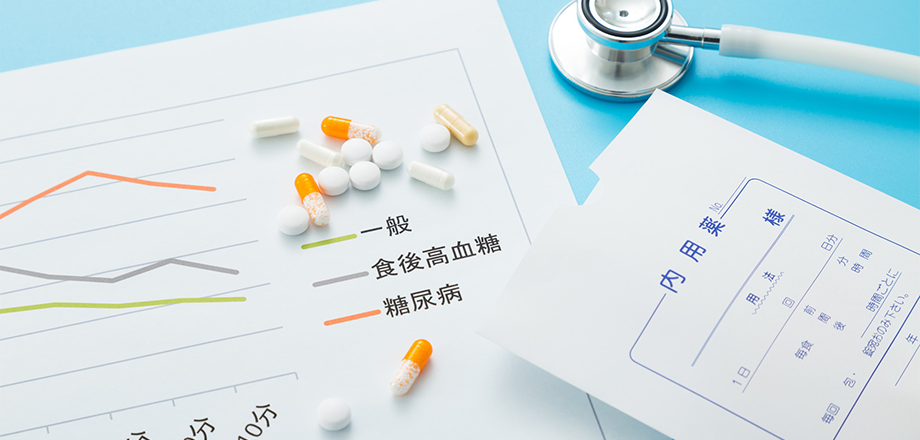
糖尿病とはどんな病気?
普段の生活の中で糖尿病という言葉を耳にする機会があると思いますが、糖尿病とはどんな病気のことなのでしょうか。
具体的には以下のような状態を指します。[注1]
“糖尿病は、インスリンというホルモンの不足や作用低下が原因で、血糖値の上昇を抑える働き(耐糖能)が低下してしまうため、高血糖が慢性的に続く病気です。”
糖尿病は自覚症状がないまま進行するケースがあり、重症化すると合併症として目、腎臓、神経に影響を及ぼす恐れがあります。
糖尿病は1型糖尿病、2型糖尿病、その他、妊娠糖尿病に分けられ、20歳以上の男女で糖尿病が疑われる人・糖尿病の可能性を否定できない人の割合は以下のとおりです。[注2][注3]
| 年齢 | 男性(調査客体:1,013人) | 女性(調査客体:1,399人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 糖尿病が強く疑われる人 | 糖尿病の可能性を否定できない人 | 糖尿病が強く疑われる人 | 糖尿病の可能性を否定できない人 | |
| 20〜29 | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 2.2% |
| 30〜39 | 1.6% | 1.6% | 2.6% | 1.8% |
| 40〜49 | 6.1% | 6.1% | 2.8% | 4.7% |
| 50〜59 | 17.8% | 11.6% | 5.9% | 13.1% |
| 60〜69 | 25.3% | 14.9% | 10.7% | 18.3% |
| 70〜 | 26.4% | 16.2% | 19.6% | 16.5% |
このように糖尿病が疑われる人の割合は年齢の増加に比例しており、60〜69歳の男性の場合、約4人に1人が糖尿病の疑いがあるといえます。糖尿病は誰でも発症する可能性があるため、事前に症状や原因を把握して対策をするとよいでしょう。
以下では糖尿病の種類別に症状の説明をします。
[注1]e-ヘルスネット「糖尿病」
[注2]厚生労働省「糖尿病」
[注3」厚生労働省「令和4年版 厚生労働白書」
1型糖尿病
1型糖尿病は自己免疫によって、インスリンを分泌する膵β細胞という細胞が破壊されてしまい、インスリンの分泌が低下する糖尿病です。[注4]
1型糖尿病はインスリン依存型とも呼ばれており、患者自身がお腹、上腕の外側、おしり、太もものいずれかに自己注射を行ない、治療を促します。[注5]
[注4]e-ヘルスネット「糖尿病」
[注5]国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「血糖値を下げる注射薬」
2型糖尿病
2型糖尿病は遺伝的な影響や生活習慣の影響によって、インスリンの効果が弱くなったり分泌されにくくなったりすることが原因の糖尿病です。[注6]
2型糖尿病の原因である生活習慣の乱れとして、食べ過ぎ、運動不足などが挙げられます。
日本国内の糖尿病患者のうち、大半を2型糖尿病が占めているとされています。[注7]
妊娠糖尿病
妊娠糖尿病とは妊娠中に発症する糖尿病です。妊娠中は胎盤などの影響で血糖値が上がりやすくなります。そのため、血糖値が一定を超えると、妊娠糖尿病と診断されます。[注8]
妊娠糖尿病で注意すべきは次のような合併症です。
母親の場合:妊娠高血圧症候群、早産
子どもの場合:巨大児
妊娠糖尿病になった場合、その後、糖尿病になりやすいとされています。
[注6]厚生労働省「糖尿病に関する留意事項」P46
[注7]厚生労働省「糖尿病」
[注8]ヘルスケアラボ「妊娠糖尿病」
初期の糖尿病症状

初期の糖尿病は自覚症状が出ることが少ないのが特徴です。
しかし、インスリンの作用が不足して高血糖の状態が続くと以下のような糖尿病症状が現れます。
・のどの渇き
・頻尿
・急な体重減少
・疲労感
さらに進行すると以下のような糖尿病症状が現れます。[注9][注10]
・足先のしびれ
・物が二重に見える
・感染症にかかりやすく重症化しやすい
[注9]厚生労働省「保健指導における学習教材集」P7
[注10]国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「血糖値を下げる注射薬」「糖尿病と感染症のはなし」
糖尿病の合併症

糖尿病症状が進行していくと、次のような合併症を引き起こす恐れがあります。[注11]
| 糖尿病性神経障害 | 手足のしびれ、感覚が鈍くなる |
| 糖尿病性網膜症 | 視力が低下し、さらに悪化すると、失明の可能性もある |
| 糖尿病性腎症 | 腎臓の働きが悪化。さらに進むと人工透析を行う必要がある |
[注11]厚生労働省「糖尿病に関する留意事項」P47
糖尿病性神経障害
糖尿病によって高血糖の状態が続くと、末梢神経の代謝に支障を来してしまいます。
その結果、不必要な物質の滞留や血管の損傷による血流の低下につながります。[注12]
これらが神経の働きを阻害することで、手足のしびれや痛みなどの感覚の異常や心臓・血圧調節の異常が起きてしまいます。
[注12]国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「神経障害」
糖尿病性網膜症
高血糖の状態が続くと、網膜の毛細血管が傷ついて失明してしまう恐れがあります。
e-ヘルスネットでは、糖尿病性網膜症を次の3つの段階に分けています。[注13]
| 単純性網膜症 | 網膜の毛細血管にコブができて詰まったり、血管の一部が破れて出血したりします。この段階では薬による治療が行われます。 |
| 前増殖網膜症 | 血管が詰まるためにそれに代わる新生血管の増殖が始まります。レーザー光線で焼き固めて新生血管ができるのを防ぐ「光凝固」という治療が行われます。 |
| 増殖網膜症 | 新生血管が増殖して出血を繰り返し、増殖膜が生じます。出血が少ないときは光凝固で治療しますが、これができないときは手術が行われます。 |
[注13]e-ヘルスネット「糖尿病網膜症」
糖尿病性腎症
高血糖の状態が続き、腎臓の機能が低下してしまうのが糖尿病性腎症です。
糖尿病性腎症は早期の段階であれば無症状ですが、進行していくと尿として老廃物を排泄しづらくなっていきます。
その結果、身体のむくみや貧血、高血圧といった糖尿病症状が現れ、最終的には人工透析が必要になります。
なお、人工透析の原因疾患として最も多いのが、糖尿病性腎症です。
e-ヘルスネットでは、人工透析の原因は糖尿病性腎症が第1位であると紹介されています。[注14]
[注14]e-ヘルスネット「糖尿病性腎症」
その他の合併症
また、糖尿病は感染症とも関係しています。
血糖値が高いと白血球のほか、免疫に関わる細胞の機能が低下して、病原菌から身体を守れなくなってしまう恐れがあります。[注15]
糖尿病によって感染しやすくなる感染症として以下が挙げられます。[注15]
・尿路感染症
・呼吸器感染症
・胆道感染症
・皮膚の感染症
・歯周病
[注15]国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「糖尿病と感染症のはなし」
まとめ
糖尿病は1型糖尿病、2型糖尿病に分けられ、国内では生活習慣が原因のひとつである2型糖尿病が大半です。
そのため、糖尿病を発症しないための1次予防として日頃から運動や食事に気を付けて生活習慣の改善を図りましょう。
また、糖尿病は発症しても症状が進行しないための2次予防で血糖値をコントロールすることが大切です。
加えて、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症といった合併症を引き起こさないための3次予防も重要です。
糖尿病症状を悪化させないためにも、異変を感じたら早期に医療機関を受診しましょう。