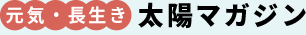不眠症とはどんな症状?原因や改善方法について解説
不眠症とは、思うように睡眠が取れなくなることです。
睡眠は心身の健康維持に欠かせないものですが、現代人の中には不眠症に悩まされている方が少なくありません。
不眠症が悪化すると日常生活に大きな支障をきたしますので、その原因や改善方法をチェックしておきましょう。
この記事では、不眠症とはどんな症状なのか、原因や主な症状、改善方法について解説します。

不眠症とは?
厚生労働省の生活習慣病予防のための健康情報サイトであるe-ヘルスネットでは不眠症を以下のとおり定義しています。
“不眠症とは、入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害などの睡眠問題が1ヶ月以上続き、日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下・食欲低下などの不調が出現する病気です。“[注1]
眠りたいのに眠れないという経験を誰しも一度はしたことがあると思いますが、多くは一時的なもので、数日〜数週間が経過すれば、元通りに眠れるようになります。
しかし、不眠症になると「寝付きが悪い」「途中で目が覚める」「寝ても疲れが取れない」といった問題がなかなか解消されず、長期間にわたって睡眠障害に悩まされるようになります。
不眠症は決して珍しい疾患ではなく、e-ヘルスネットによれば、以下のとおり日本人の多くが不眠症に悩んでいることがわかります。
“日本人を対象にした調査によれば、約5人に1人が「睡眠で休養が取れていない」、「何らかの不眠がある」と回答しています。加齢とともに不眠は増加します。60歳以上の方では約3人に1人が睡眠問題で悩んでいます。“[注1]
そのため、不眠症は国民病・現代病とも言われています。
[注1]e-ヘルスネット「不眠症」
不眠症のタイプ
不眠症とは、大きく分けて以下4つのタイプに分類されます。[注1]
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 入眠障害 | 寝付きが悪くなる |
| 中途覚醒 | 眠りが浅く、途中で何度も目が覚める |
| 早朝覚醒 | 早朝に目が覚めてしまう |
| 熟眠障害 | ある程度眠っても熟睡したという満足感が得られない |
どのタイプの不眠症になるかは個人差がありますが、いずれの場合も長引けば長引くほど日常生活に影響を及ぼします。
そのため、きちんと原因を追究した上で、適切な対処を取ることが大切です。
不眠症を引き起こす原因

長い時間、眠っていれば不眠症にならないと思われがちですが、実のところ睡眠時間はあまり問題ではありません。
なぜなら、必要な睡眠時間には個人差があり、10時間眠らないと睡眠不足になるという人もいれば、わずか3時間ほどの睡眠で間に合うという人もいるからです。
不眠症の概要でも説明しましたが、不眠症は睡眠時間が極端に短いことを意味するものではなく、不眠によって日中にさまざまな不調が現れる状態のことです。
短時間睡眠でも、日中に不眠の症状が現れていないのなら不眠症には該当しません。
では、不眠症とはどのような原因で引き起こされるのでしょうか。
厚生労働省による睡眠対策情報が掲載されている「健康づくりのための睡眠指針2014」によると、不眠症の原因は以下5つに分類されます。[注2]
●精神整理性不眠、原発性不眠
●薬原性不眠
●身体疾患における不眠
●精神疾患における不眠
●臓器質性疾患における不眠(認知症を含む)
それぞれの原因について、かんたんに解説します。
[注2]厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」P56,P57
精神整理性不眠、原発性不眠
毎晩眠れるかどうかを心配することが強い不安や緊張をもたらして不眠の原因になります。さらに眠ろうと努力することで不安や緊張が増し、かえって眠れなくなる悪循環です。そのうえ、横になっただけで「また眠れないのでは」と苦痛を感じることから条件反射的に不安・緊張が高まり、さらに眠れない状態をつくることが原因になると考えられています。
薬原性不眠
薬の副作用が不眠の原因となるケースが「薬原性不眠」です。
抗パーキンソン病薬や副腎皮質ステロイド、降圧薬などが不眠の原因となる薬剤として知られています。
身体疾患における不眠
身体疾患がある場合、かゆみや痛みなどの身体的な不快感が睡眠を妨害し、不眠の原因となることがあります。
不眠の原因となる身体疾患としては、慢性の痛みでは頚椎症や腰痛が最も多いとされています。
精神疾患における不眠
精神疾患において、不眠などの睡眠障害は頻度の高い症状であるとされています。
うつ病の場合、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒に加え、熟睡感欠如、休息感欠如、朝の離床困難が合併してくることが特徴的です。
うつ病が疑われた場合には、速やかに専門医に相談しましょう。
脳器質性疾患における不眠(認知症を含む)
アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患、脳血管障害、脳腫瘍や頭部外傷が不眠の原因となることがあります。
これらは脳障害が睡眠機構を妨害して不眠の原因となる場合と、神経疾患による身体症状が原因で不眠となる場合があります。
不眠症による症状
不眠症とは、睡眠問題が1ヶ月以上続き、日中にさまざまな不調が出現する疾患と説明しましたが、ここでいう「不調」とは、倦怠感・意欲低下・集中力低下・抑うつ・頭重・めまい・食欲不振などを指します。[注1]
これらの不調は複数重なることもあり、ひどい場合は日常生活に大きな支障をきたしたり、健康状態が悪化したりする要因になります。
また、何日も眠れない日が続くと「今日も眠れなかったらどうしよう」と不安になり、早く眠らなければと焦れば焦るほど目が冴えてしまうのは、不眠症の方が共通して経験する不安です。
一時的だった不眠が慢性化してしまう背景には、このような「不眠恐怖」があります。[注1]
不眠の原因の中には一過性で終わるものも珍しくないのですが、不眠恐怖が慢性化し、不眠症になってしまうケースも少なくありません。
不眠状態が長く続く場合は、自然に改善されるのを待つよりも、何らかの対策を講じてケアすることをおすすめします。
不眠症の改善方法

不眠症とはさまざまな原因から引き起こされますが、改善方法は、薬物を使用しない「非薬物療法」と、不眠のタイプに合わせた薬物を処方する「薬物療法」の2つに分類されます。
ここでは、それぞれの改善方法について詳しく説明します。
非薬物療法
不眠症の原因の多くは日常生活と密接な関係があります。
生活習慣や普段の気の持ちようを変えれば、不眠症の原因が解消され、症状を緩和させることが可能となります。
不眠症の改善につながる非薬物療法の具体的な例を4つご紹介します。
目覚めたら朝日を浴びる
太陽の光には、体内時計を調整するはたらきがあり、光を浴びてから14時間目以降に眠気が生じやすくなると言われています。
たとえば、朝7時に朝日を浴びた場合、14時間目に当たる夜21時以降には自然と眠気が訪れ、規則正しい生活リズムをつくることができます。
なお、夜間に強い照明を浴びると体内時計が乱れ、夜の寝付きが悪くなるほか、寝起きがつらくなります。
就寝時間や起床時間はなるべく一定に保ち、仕事のない休日もリズムを崩さないようにしましょう。
睡眠環境を整える
睡眠は周囲の環境から大きな影響を受けます。
寝室が明るすぎたり、騒音がしたり、暑すぎるまたは寒すぎたりすると、寝付きや睡眠の質が悪くなります。
就寝する際は照明を落とす、騒音が気になる場合は耳栓を使用する、空調を活用するなど、いろいろな工夫を取り入れて良好な睡眠環境を整えましょう。
夜勤などで日中眠らなければならない場合は、遮光カーテンを利用するのもおすすめです。
また、寝る前にはカフェインや寝酒は控える、リラックスできる時間をつくるなど、心身を睡眠に適した状態に調整するのも有用な方法のひとつです。
日頃から適度な運動をする
日中にほどよい運動を行っておくと、心地良い眠りにつきやすくなります。
できれば午後を中心に、軽く汗ばむくらいの運動をする習慣をつけましょう。
なお、激しい運動はかえって眠りを妨げる要因になりますので、軽い運動を定期的に続けるのがコツです。
睡眠時間にこだわり過ぎない
日本人の平均睡眠時間は7時間とされていますが、前述の通り、その人に適した睡眠時間はまちまちです。
「◯時間眠らなければならない」という固定観念を持つと、かえって焦りや不安を生み出してしまい、不眠の原因になる可能性があります。
どうしても眠くならないときは思い切って起きてしまい、気分転換してもよいでしょう。
薬物療法
非薬物療法を試しても不眠症が治らない場合は、精神科や心療内科などを受診し、医師に相談してみましょう。
不眠について相談するだけでも心が軽くなり、不眠症が改善する場合もあります。
また、症状によっては不眠のタイプに合わせた睡眠導入剤も処方してもらえます。
睡眠薬に抵抗を覚える方も少なくありませんが、医師の指導のもと、正しく服用すれば早期改善の助けになります。
まとめ
不眠症とは、環境や心理などの影響を受けやすく、誰がかかってもおかしくない疾患です。
不眠が続くと不眠恐怖や緊張などから睡眠へのこだわりが強くなり、悪循環に陥る可能性が高くなります。
生活習慣を見直すのはもちろん、必要に応じて専門家に相談し、適切なアドバイスや治療を受けることをおすすめします。