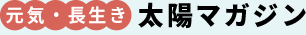子どもが発熱したときについて。対処法や取るべき行動を知っておこう
子どもが急に熱を出すと、今すぐ病院に連れて行った方がいいのか、このまま様子を見るべきか、悩んでしまうこともあるでしょう。
子どもの発熱自体はさほど珍しいことではありませんが、中にはすぐに対処しなければならない症状もありますので注意が必要です。
この記事では、子どもが発熱する原因や、受診の目安、家での対処法などについて解説します。

子どもの発熱について
厚生労働省では、保育所における「登園を控えるのが望ましい場合」の目安として、以下を目安としています。[注1]
・24時間以内に38℃以上の熱が出た場合や、又は解熱剤を使用している場合。
・朝から37.5℃を超えた熱があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく朝食・水分が摂れていないなど全身状態が不良である場合。
1歳以下の乳児の場合はとくに体温が高いため、38℃以上の熱があるか、あるいは平熱より1℃以上高いときは発熱したとみなし、登園を控えることを推奨しています。
また、子どもの発熱の特徴として、一度下がったと思っても、再び熱が上がってくることがありますが、まずは慌てずに子どもの症状や様子をよく観察し、適切な対応を心がけるようにしましょう。
[注1]厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」(2018年改訂版)
子どもが発熱する原因は?
子どもが発熱する原因のほとんどは、ウイルス性感染症への白血球による免疫反応ですので、さほど心配する必要はありません。体には、外から侵入してきたウイルスや雑菌などの異物を撃退するための免疫力が備わっています。
異物を撃退する役割を担っているのが、血液に含まれる白血球ですが、平熱よりも高い温度で動くため、白血球が活動すると自然と体温が上昇します。
発熱するのは、白血球が異物を撃退しようとしている証拠ですので、本来は解熱剤などで無理に熱を下げる必要はありません。
なお、子どもの発熱の原因のほとんどはウイルス性感染症です。[注2]
ウイルス性感染症の多くは抗菌薬が効かないため、基本は自宅で様子を見ることになります。
もちろん、咳が酷くて眠れない、頭痛を伴って苦しそうだという場合は、医療機関を受診し、症状を緩和するための薬を処方してもらうのもひとつの方法です。
[注2]厚生労働省「上手な医療のかかり方」P26
子どもがかかりやすいウイルス性感染症
子どもがかかりやすいウイルス性感染症には以下のようなものがあります。
・扁桃炎
・気管支炎
・インフルエンザ
・はしか
・おたふく風邪
・水ぼうそう
・プール熱(夏季)
このうち、はしかやおたふく風邪、水ぼうそうに関しては予防接種があり、ある程度は罹患のリスクを抑えることができます。
一方、扁桃炎や気管支炎、プール熱に関しては予防接種やワクチンがなく、喉が弱い子どもは毎年のようにかかることもあります。
また、インフルエンザには予防接種がありますが、流行するウイルスの型や系統の割合は国や地域、年によって異なるため、予防接種を受けても罹患する場合があります。
なお、インフルエンザに関しては治療薬があり、投与すれば発熱などの症状はすぐに治まります。
インフルエンザは秋冬に流行しやすいため、その時期に高熱が出たら医療機関でインフルエンザの検査を受けた方がよいでしょう。
発熱したらすぐに受診したほうがいいの?

前述の通り、子どもの発熱のほとんどは免疫反応によるものなので、多くの場合はすぐに受診を必要としません。
しかし、発熱以外に気になる症状がある場合は、速やかに医療機関を受診した方がよいこともあります。
子どもが発熱した際の医療機関を受診する目安
厚生労働省では、保育所における保育中の対応について、以下のような対応を推奨しています。[注1]
| 保護者への連絡が望ましい場合 | 至急受診が必要と考えられる場合 |
|---|---|
| 38℃以上の発熱があり、 ・元気がなく、機嫌が悪いとき ・咳で眠れず目覚めるとき ・排尿回数がいつもより減っているとき ・食欲なく水分が摂れないとき ※熱性けいれんの既往児が37.5℃以上の発熱があるときは医師の指示に従う |
38℃以上の発熱の有無に関わらず、 ・顔色が悪く、苦しそうなとき ・小鼻がピクピクして呼吸が速いとき ・意識がはっきりしないとき ・何度も嘔吐や下痢があるとき ・不機嫌でぐったりしているとき ・けいれんが起きたとき |
なお、3ヶ月未満の子どもに関しては、38℃以上の発熱があるときも速やかに受診するよう呼びかけています。
逆に、生後3ヶ月以上の子どもの場合、熱が38℃を超えたとしても、他に症状がなく、水分も摂れている場合は、急いで受診する必要がないことが多いです。
場合によっては医療機関で処方された解熱剤を飲んでも熱が下がらないことがありますが、気になる症状がなく、少しでも眠れているようなら再度受診する必要はないでしょう。
また、子どもによっては40℃以上の熱を出すこともありますが、通常、高熱が原因で脳に悪影響が及ぶことはありません。
熱が40℃を超えたからと言って慌てるのではなく、水分が摂れていて、意識がはっきりしているようなら自宅で様子をみてもよいでしょう。
ただし、自宅でケアしても症状が改善しない場合は、医療機関を受診することをおすすめします。
[注1]厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」(2018年改訂版)
どう対処したらよいかわからない場合は相談しよう
「病院が閉まっている休日や夜間に発熱した場合はどうすればいいのかわからない」「受診すべきか判断がつかない」という場合は、子ども医療電話相談事業に相談しましょう。
子ども医療電話相談事業とは、対処法や受診の必要性について判断に迷った際、小児科医や看護師に電話で相談できるサービスです。[注3]
全国同一の短縮番号である「#8000」をプッシュすれば、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医や看護師が子どもの症状に応じた適切な対処や、受診の必要性をアドバイスしてくれます。
#8000の実施時間帯は都道府県によって異なりますが、おおむね夜間から翌朝まで対応していますので、子どもの症状への対処に迷ったらすぐに相談してみましょう。
[注3]厚生労働省「子ども医療電話相談事業(♯8000)について」
子どもが発熱したときに家で取るべき対処法

気になる症状がなく、発熱のみの場合は、基本的に自宅でケアすることになります。
ここでは子どもが発熱した際に、家で取るべき対処法を5つご紹介します。
安静にする
発熱しているときは体力を消耗しますので、とにかく安静にして過ごしましょう。
保育園などに通っている場合は休ませ、基本は布団やベッドで静かに寝かせておきます。
環境温の調節
子どもの手足に触れてみて、冷たいと感じたときはエアコンなどで部屋の温度を上げます。
逆に手足が温かくなったら、汗をかきすぎないよう、薄着にして涼しい状態にしましょう。
一枚着せる、脱がせるなど、着るもので調節するのも効果的です。
クーリング
熱があるときは、太い血管が通っている場所を重点的に冷やすのが効果的です。
具体的には、首の横、脇の下、足の付け根などに水で濡らしたタオルを当てたり、ぬるま湯で体を拭いたりして、体を冷やします。
冷却シートは便利ですが、子どもが誤って飲み込んでしまうと窒息などの原因になりますので、使用は控えた方が無難です。
水分補給
発熱しているときはこまめに水分を補給させましょう。
水よりも、体内への吸収率が高い経口補水液を与えるのがベストです。
一気に飲ませる必要はなく、少量をこまめに与えていればOKです。
着替え
熱が下がってくるとしだいに汗をかいてきます。
とくに小さな子どもはもともと汗っかきなので、定期的に着替えをして汗冷えを予防しましょう。
解熱剤はむやみやたらに使用しない!
子どもが熱で苦しい思いをしていると、解熱剤を使って早く熱を下げてあげたいと考える親御さんは多いでしょう。
しかし、前述の通り、子どもの熱のほとんどは白血球による免疫反応なので、無理に解熱剤を使って熱を下げる必要はありません。
発熱のもとになっているウイルスが排除されなければ、解熱剤を使って一時的に熱を下げたとしても、再び熱が上がってしまいますので、むやみやたらに使用しない方がよいでしょう。
ただ、発熱によって痛みや倦怠感があると、寝付きが悪くなったり、強いストレスを感じたりして、子どもの体に大きな負担がかかってしまうこともあります。
水分を十分にとれている場合は様子見で良いですが、痛みや倦怠感のせいで水分補給が難しい、よく眠れないなどの症状が出ている場合は、適切に解熱剤を使用して症状の緩和に努めた方がよいでしょう。
解熱剤の用法・用量については、厚生労働省が発表している「第2回小児薬物療法検討会議」において、以下が妥当であるとしています。[注4]
| 体重1kgあたりの使用量 | 1回10〜15mg |
| 使用間隔 | 4〜6時間以上 |
| 1日の総量 | 60mg/kgが限度 |
用法・用量に関しては決して自己判断せず、薬を処方した医師に教えてもらった方法を守って使用することが大切です。
もしわからないことがあったら、事前に医師に相談し、指示を仰ぐことをおすすめします。
[注4]厚生労働省「アセトアミノフェンの『小児科領域における解熱』報告書作成中間サマリー」
まとめ
子どもの発熱のほとんどは、白血球による免疫反応ですので、さほど心配する必要はありません。
気になる症状がなければ、自宅で安静にした上で、水分補給やクーリングなどで対応すれば、徐々に熱は下がってきます。
ただし、顔色が悪いときや、呼吸が速いとき、意識がはっきりしていないときなどは、高熱の有無にかかわらず、速やかに医療機関を受診しましょう。
なお、解熱剤は必要に応じて使ってもかまいませんが、一時的に熱を下げるものなので、根本的な解決にはなりません。
むやみやたらに解熱剤を使うよりは、子どもの様子を観察し、必要なホームケアを行ったり、相談できる機関にアドバイスを求めたりして、正しい対応を取れるようにしておきましょう。