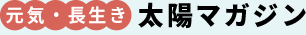発達障害とは?生まれつきの特性?発達障害についてわかりやすく解説!
同年代の子と比べて、我が子の発達が遅れていたり、異なる点が見られたりすると、「もしかして発達障害では?」と不安になることがあります。
発達障害がある場合、日常生活で適切な配慮やサポートが必要になります。
この記事では、発達障害とはどんな障害なのか、基本的な知識と主な症状、発達障害のサインや、サポートのポイントについてわかりやすく解説します。

発達障害とはどんな障害?
発達障害とは、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。[注1]
外見には特に変化がないため、障害があると気付かれにくい一方、日常生活や社会生活を送る上でさまざまな支障をきたすことから、生きづらさを感じる人も少なくありません。発達障害とは、一人ひとり異なる困難があるものだと理解しておくことが大切です。
発達障害とは何か、正しい理解と知識を深め、子どもに適したサポートを行いましょう。
[注1]厚生労働省「発達障害」
発達障害の症状

発達障害には、複数の種類があります。
ここでは主な発達障害の種類と、各々の症状、子どもが困っていることをまとめました。
| 発達障害の種類 | 主な症状 | 主な子どもの困りごと |
|---|---|---|
| 自閉スペクトラム症(ASD) |
・他者とのコミュニケーションが苦手 ・同じ行動や活動を繰り返す |
・なかなか友達を作れない ・友人関係が一方的になる |
| 注意・欠如多動症(ADHD) |
・注意力の欠如 ・落ち着きがない |
・授業中にじっとしていられない ・不注意でミスを起こしやすい |
| 学習障害(LD) |
・読字障害 ・書字障害 |
・読み書きが苦手で授業についていけない |
| チック症 |
・突然大声を出す ・まばたきや首振りなどの動作を繰り返す |
・「落ち着きがない子」「迷惑をかける子」と捉えられることがある |
| 吃音 | 滑らかに話すことができない |
・周りから笑われる ・話し方を注意される |
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症とは、社会的コミュニケーションにおいて持続的な困難さが見られたり、日常で決まった行動や関心、動作のパターンを持ったりする障害のことです。
e-ヘルスネットでは、自閉スペクトラム症について以下のように記載しています。
“これまで、自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていましたが、2013年のアメリカ精神医学会(APA)の診断基準DSM-5の発表以降、自閉スペクトラム症(ASD;Autism Spectrum Disorder)としてまとめて表現するようになりました。”
[引用]e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」
具体的な症状としては、言葉の発達に遅れが見られる、オウム返しが多い、会話が成立しないなどがあり、他者とコミュニケーションを取ったり、関係を築いたりするのが苦手です。
また、日常生活で同じ行動を繰り返したり、特定のことに強いこだわりを見せたりする症状もみられます。
こうした症状から、自閉スペクトラム症がある子どもはなかなか友達を作れなかったり、友人関係が一方的になったりすることが多く、人間関係で悩みやすい傾向にあります。
注意・欠如多動症(ADHD)
ADHD(注意欠如・多動症)は、「不注意」と「多動・衝動性」を主な特徴とする発達障害の概念のひとつです。[注2]
同年代の子に比べて落ち着きがなく、学校では授業中に立ち歩いたり、先生の話をじっと聞いていたりするのが困難です。
作業をしていても不注意でミスを起こしやすく、まわりから「注意が足りない」「失敗しやすい」とみなされることがあります。
学習障害(LD)
学習障害(限局性学習症、LD)は、読み書き能力や計算力などの算数機能に関する、特異的な発達障害のひとつです。[注2]
困難を感じるポイントには違いがあり、読みが苦手な場合は「読字障害」、書くことが苦手な場合は「書字障害」などと呼ばれることもあります。
たとえば書字障害のある子どもの場合、メモやノートを取ることに集中しすぎて、授業の内容がわからなくなることがしばしば起こります。
日本では板書をともなう授業が多いため、読み書きが苦手だと学習に支障をきたすケースが多く、勉強についていけないなどの問題が生じやすくなります。
チック症
チック症とは、思わずすばやい体の動き(運動チック)や発声(音声チック)が出てしまう障害のことです。[注1]
たとえば、自分の意思とは無関係に突然大声を出したり、まばたきや首振りなどの動作をすばやく繰り返したりします。
チック自体はさほど珍しい症状ではなく、成長するにつれて自然と収まるケースも多いのですが、運動チックまたは音声チックが一年以上にわたって持続し、かつ日常生活に支障をきたす場合は「トゥレット症」と診断されます。
運動または音声チックがあると、「落ち着きのない子」「授業中に迷惑をかける子」とみられる可能性があります。
吃音
吃音とは、滑らかに話すことができないという状態をいいます。[注2]
同じ音を繰り返したり、引き伸ばしたり、うまく言葉を出せずに間が空いてしまったりするので、他者とスムーズに会話できない場合があります。
吃音のある子どもは、しばしば周りから笑われたり、ゆっくり話すよう注意されたりするので、話すことに消極的になってしまうケースも少なくありません。
[注1]厚生労働省「発達障害」
[注2]政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう?」
発達障害に早く気づくには?気づいたらどうする?

子どもの発達障害に早く気づくためには、日頃から子どもの様子を観察し、特定のサインを見逃さないよう注意する必要があります。
特定のサインをもとに専門の機関を受診し、発達障害と診断されたら、日常生活や社会生活にできるだけ適応できるよう、適切な配慮を行いましょう。
ここでは発達障害に早く気づくためにチェックしたいサインと、気づいた後のサポートの方法について説明します。
発達障害のサイン
発達障害のサインは、障害の種類によって異なります。
| 障害の種類 | サイン(一例) |
|---|---|
| 自閉スペクトラム症 |
・目を合わせない ・指さししない ・笑い返さない ・後追いしない ・他の子に関心を示さない ・言葉の発達に遅れがある ・こだわりが強い |
| 注意欠如・多動症(ADHD) |
・落ち着きがない ・じっと座っていられない ・授業中に席を離れる ・しゃべりすぎる ・順番を待てない |
| 学習障害(LD) |
・黒板などの文字の読み書きが難しい ・簡単な計算ができない |
| チック症 |
・急に大声を出す ・大きなうなり声をあげる ・首を激しく振る ・顔を何度も叩く |
| 吃音 |
・「ああああ明日」など、単語の一部を何度も繰り返す ・言葉がつかえてすぐ返事ができない ・「ぼーーーくは」など、初めの音を引き伸ばす |
この他にも、発達障害のサインはいろいろあります。
専門家に相談したり、アドバイスを受けたりしながら、それぞれの障害を正しく理解することで、子どもがストレスを溜めないようサポートしてあげましょう。
子どもが発達障害と診断されると、親は不安な気持ちになりますが、しっかり向き合って対処すれば、日常生活や社会生活に少しずつ適応できるようになります。
発達障害のサポートのポイント
発達障害と診断されたら、障害の種類に応じて適切なサポートを行う必要があります。
ここでは障害ごとにサポートのポイントをまとめました。
自閉スペクトラム症(ASD)へのサポート
自閉スペクトラム症のある子どもは、他者とのコミュニケーションが苦手だったり、行動や動作がパターン化したりする傾向にあります。
やり取りや説明が複雑になるとコミュニケーションを取りづらくなるので、できるだけシンプルな伝え方を心がけたり、簡単な手順を実演してみせたりするのが効果的です。
注意欠如・多動症(ADHD)へのサポート
注意欠如・多動症は落ち着きがなく、長い間集中するのが困難な傾向にあります。
何か伝えたいことがある場合は、短く簡潔な言葉で説明するよう努めましょう。
また、座らせる時は気が散りにくい座席を指定するなどの工夫を採り入れるのも有効です。
学習障害(LD)へのサポート
学習障害と一言にいっても、どの能力を苦手としているのかは人それぞれです。
たとえば聞くことは得意だけれど、書くことは苦手など、同じ学習障害がある子どもでも得手・不得手には差があります。
得意な部分は情報の理解や表現方法に積極的に活用しつつ、苦手なところは課題の量や質を適度に加減しながら、ゆっくりとしたペースで学習できるよう配慮しましょう。
まとめ
発達障害とは生まれつきの脳機能の発達に関連した障害のことです。
対人関係を築くのが難しい自閉スペクトラム症(ASD)をはじめ、注意・欠如多動症(ADHD)や学習障害(LD)、チック症、吃音など複数の種類があり、それぞれ症状や配慮のポイントに違いがあります。
まずは子どもの様子を丁寧に観察し、発達障害のサインが見られるようなら、専門機関を受診して相談しましょう。
生活環境や年齢、障害の程度はさまざまですが、適切な配慮やサポートを行えば、日常生活や社会生活で感じる困難や障壁を軽減することは可能です。
障害の種類に応じて適切なサポートを心がけましょう。