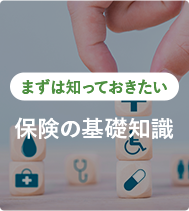医療保険
手術給付金の基礎知識!
対象になる手術は?いくら受け取れる?
この記事では、手術給付金の仕組みや対象となる手術、これから医療保険に加入する際に見るべき手術給付金のポイントについて解説します。
この記事を読んでいる方は
以下の商品も閲覧しています
閉じる
日帰り入院・手術も安心!
急な入院・手術に一時金で備えられる
そもそも手術給付金とは?
手術給付金とは、医療保険に加入している方が、病気やケガが原因で所定の手術を受けたときに受け取れる給付金のことです。
給付金の支払回数は保険会社や商品によってさまざまに設定されており、施術開始日から60日に1回など、支払い制限を設定している場合や、保険期間内であれば何度でも支払われる場合もあります。また、同じ日に複数の手術を受けた場合、それらの手術のうち給付支払額が高い手術についてのみ給付金が支払われるのが一般的です。
入院給付金は入院していることが前提条件ですが、手術給付金は入院のない外来手術であっても給付金を受け取ることができます。保険会社によって異なりますが、多くの保険会社では入院をともなう手術と外来手術とで、別々の給付条件を設定して給付をしています。
手術給付金の給付対象となる手術
手術給付金は、すべての手術を保障してくれるわけではありません。給付対象になる手術とならない手術がありますので、注意が必要です。
手術給付金の対象となる手術とはどんな手術なのかを知っておきましょう。
手術給付金の対象となる手術は、医療保険によって異なる
手術給付金の対象となる手術は、加入する医療保険によって2つのタイプに分かれます。
公的医療保険に連動する約1,000種の手術
公的医療保険制度の対象となる約1,000種の手術が給付対象となる医療保険です。現在の医療保険では、このタイプが主流です。
公的医療保険と連動するため、これまで対象外だった手術が新たに対象となる場合もあり、医療技術の進化に対応した形といえます。
自分が受けた手術が手術給付金の対象になり得るかどうかを判断するのは困難です。そのため、手術を受けたときは医師に、公的医療保険制度の対象になるかどうかを尋ねたほうが安心です。
保険会社所定の88種の手術
保険会社の約款で定める88種に分類された手術が対象となる医療保険です。88種ときくと1,000種と比べてとても少なく感じますが、これは対象となる手術等を大きく分類しているためで、手術の数として600種類前後はあり、一般的な手術はカバーされています。
手術給付金の給付対象とならない手術

手術給付金の対象とならない手術について、2つのパターンを解説します。
給付の対象になるかどうかの取り扱いは保険会社によって異なります。気になる場合は各社に確認しましょう。
保険加入前に発生した病気やケガによる手術
医療保険に加入する前から発生していた病気やケガを原因とする手術は、手術給付金の対象外です。病院で手術を勧められた後に、手術給付金を目的に医療保険に入るというようなことはできませんので注意しましょう。
公的医療保険適用外の手術(治療を目的としていない手術)
公的医療保険の適用外となる手術は手術給付金の対象外です。具体的には、以下のような手術が挙げられます。
●美容整形手術
●視力矯正にともなう手術(レーシック)
●正常分娩による手術
これらは治療を目的としない手術のため、公的医療保険は適用されず、手術給付金の対象にはなりません。[注1]
[注1]公益財団法人 生命保険文化センター「医療保障に関するQ&A」
手術給付金っていくらぐらい受け取れるの?
手術給付金が実際にいくら受け取れるかどうかは、加入する医療保険によって、大きく2つのパターンに分かれます。
金額が一律で決まっている
給付対象となる手術の内容にかかわらず、手術1回につき〇円や、入院日額の〇倍といったように、一律で金額や給付倍率が決まっているパターンです。
この場合、多くの保険会社で、入院をともなう手術と外来手術とで異なる金額または倍率を設定しています。
手術によって倍率が決まる
対象となる手術の内容によって給付倍率が異なるパターンもあります。このパターンは、保険会社の約款に定める手術を対象とする医療保険に多く、入院給付金日額に手術の種類に応じた給付倍率を乗じた手術給付金が受け取れます。
比較的軽度な手術は倍率が低く、重大手術ほど倍率が高くなっています。対象となる手術内容や給付倍率は、保険会社によって異なります。
この記事を読んでいる方は
以下の商品も閲覧しています
医療保険に加入する際に見る手術給付金のポイント
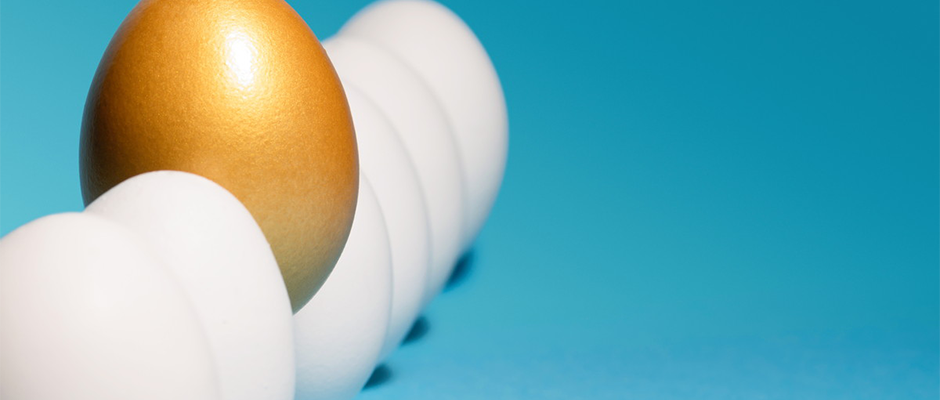
医療保険への加入を検討する際に、手術給付金について確認すべき4つのポイントをご紹介します。保険選びの参考にしてください。
手術給付金の給付倍率
手術の保障を手厚くしたい方は、手術給付金の給付金額が高い医療保険を選択しましょう。
保険商品によっては、入院をともなう手術だけでなく、外来手術を手厚くすることも可能です。また、重大手術の保障を手厚くすることもできます。
ただし、手術給付金を手厚くすると、保険料も上がります。保障と保険料のバランスを意識して検討するようにしましょう。
手術給付金の給付条件
手術給付金は対象となる手術であれば、何度でも給付が受けられます。しかし、保険会社によっては以下のような条件が設定されている場合もあります。
●施術開始日から60日に1回を限度とする
●1日に複数回の手術を受けた場合は、1回分のみ給付する
●放射線治療は60日に1回を限度とする
なかなか目につきにくいポイントですので、気になる場合は保険会社にしっかりと確認しましょう。
女性疾病やがんの備え
女性特有の疾病や、男女問わず罹患リスクの高いがんの保障を重視したい場合などは、特約によって保障を手厚くすることも可能です。
治療期間が長引いたり、治療費やその他の費用が高額になったりしやすい疾病に対して、給付金が上乗せできるかどうかも保険選びのポイントです。
先進医療への備え
ほとんどの保険会社で付加することのできる先進医療特約は付加することがおすすめです。
先進医療とは、厚生労働大臣が承認した高い医療技術のことで、その技術料は公的医療保険の対象とならないため全額自己負担となり、高額となる場合がある治療です。
先進医療特約は、保険会社によって上限金額は異なりますが、かかった技術料を保障してくれます。医療技術が進化する中、選択肢の幅を広げ、自分に合った治療方法を選ぶことも重要です。経済的な理由により手術が受けられないということがないよう、先進医療の保障はカバーしておきましょう。
太陽生命の手術保障保険は公的医療保険制度または先進医療の対象となる約1,000種類の手術・放射線治療を保障!
太陽生命ダイレクト スマ保険の「医療保険(入院一時金保険、手術保障保険等)」は日帰りの入院や手術にも対応しており、短期の入院・手術でもまとまった一時金を受け取ることができるので急な入院や手術にもしっかりと備えることができます。
さらに、太陽生命の医療保険ならお客様のニーズに合わせて自由に組み合わせができますのでご自身に希望にあった保障内容で申し込みいただけます。
商品のポイント
入院一時金保険
「入院一時金保険」は病気やケガで1日以上入院したときに入院一時金をお受け取りいただけます。日帰り入院でもまとまった一時金が受け取れるため、短期入院にも手厚く備えることができます。
女性入院一時金保険(女性向け)
入院一時金保険と組み合わせて申し込むことができます。女性疾病(産じょく合併症、ぼうこう炎、鉄欠乏性貧血、甲状腺の障害などの女性特有の病気や生活習慣病)で入院した場合に手厚く備えることができます。
生活習慣病入院一時金保険(男性向け)
入院一時金保険と組み合わせて申し込むことができます。生活習慣病(糖尿病、高血圧症、心疾患、脳血管疾患など)で入院した場合に手厚く備えることができます。
災害入院一時金保険
入院一時金保険と組み合わせて申し込むことができます。所定の感染症やスポーツ中の事故などの災害で入院した場合に手厚く備えることができます。
手術保障保険
入院一時金保険と組み合わせて申し込むことができます。入院の有無にかかわらず、公的医療保険制度または先進医療の対象となる約1,000種類の手術・放射線治療を保障します。
これらの保険を自由に組み合わせることができるため、お客様のニーズにあわせて申し込むことが可能です。
太陽生命ダイレクト スマ保険のホームページでは、性別と生年月日を入力するだけで簡単に保険料を試算することができますので、気になった方はぜひ、お気軽に保険料の試算をしてみてください。
この記事を読んでいる方は
以下の商品も閲覧しています
まとめ
医療保険の保障のひとつである手術給付金は、約款に定められている手術のみが支払いの対象となり、公的医療保険に連動している約1,000種か、保険会社が指定している88(89)種のどちらかとなります。治療を目的としない美容整形や視力矯正手術、正常分娩による手術は対象外になるため注意しましょう。
給付される金額や倍率、給付条件については保険会社によって異なります。加入時にしっかりと確認し、十分に納得したうえで加入するようにしましょう。
太陽生命ダイレクト「スマ保険」の医療保険は、急な入院・手術にも一時金で備えることができます。手術保障保険は、公的医療保険に連動する約1,000種類の手術を保障の対象としており、外来手術でも保障の対象となるので安心です。給付金は一時金として受け取ることができるので、急にまとまったお金が必要になった場合でも、使途を選ばず幅広く対応することができます。入院や手術の保険を検討されている方はぜひチェックしてみてください。
※当コラムは2023年4月時点の情報をもとに作成しております。
当コラムに記載している公的制度に関する取扱いについては改正などで将来変更となることがあります。個別の取扱いについては、最寄りの市役所等または公的機関のホームページにてご確認願います。