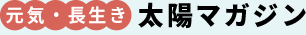配偶者控除とは?計算方法や手続きの方法をわかりやすく解説!
配偶者の所得が条件を満たしている場合、配偶者控除として納税者本人の所得が控除される場合があります。配偶者控除とは異なる配偶者特別控除もあります。
この記事では配偶者控除や配偶者特別控除の条件、それぞれの違いなどについて解説します。

配偶者控除とは?
配偶者控除とは控除対象配偶者がいる場合に、一定金額の所得控除が納税者に対して認められる制度です。控除対象配偶者には一般の配偶者に加えて老人控除対象配偶者があります。老人控除対象配偶者はその年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人が当てはまります。
配偶者控除を受ける条件
配偶者控除を受けるには、12月31日時点で次の4つの条件を満たしている必要があります。[注1]
“
- (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- (2)納税者と生計を一にしていること
- (3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと “
事業専従者とは、個人事業主と生計をともにしている配偶者や15歳以上の親族といった家族従業員を指します。青色申告、白色申告ともに事業専従者は配偶者控除の対象とならない一方で、青色申告、白色申告で確定申告を行う場合、条件を満たせば給与を経費として扱えます。[注2]
なお、配偶者控除を受けるには配偶者の条件に加えて、控除を受ける納税者の所得が1,000万円以下でなければなりません。
[注1]国税庁「No.1191 配偶者控除」(令和4年4月1日現在)
[注2]国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」(令和4年4月1日現在)
配偶者特別控除とは
配偶者控除を受ける条件として、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であることが設けられているのに対して、配偶者特別控除であれば、配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があった場合でも控除を受けられる可能性があります。
配偶者特別控除を受けるための条件
配偶者特別控除を受けるための条件は次のとおりです。[注3]
“
- (1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- (2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
- イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
- ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
- (3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
- (4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
- (5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。”
合計所得金額1,000万円以下という条件は、給与収入のみの年収で考えると、1,195万円以下(1,000万円+給与所得控除195万円)である必要があります。[注4]
[注3]国税庁「No.1195 配偶者特別控除」(令和4年4月1日現在)
[注4]国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和4年4月1日現在)
配偶者控除との違い
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは条件と控除額です。配偶者控除と配偶者特別控除の条件の違いは次のとおりです。
● 配偶者控除:配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
● 配偶者特別控除:配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)
このように配偶者の年間合計所得が48万円を超えたとしても、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
また、配偶者控除と配偶者特別控除は控除額にも違いがあります。配偶者控除の控除額は最大38万円、最小13万円なのに対して、配偶者特別控除は最大38万円、最小1万円です。
配偶者控除、配偶者特別控除の控除額
配偶者控除と配偶者特別控除額の違いは次のとおりです。[注5][注6]

配偶者控除の場合、納税者本人の所得が900万円以下であれば最大38万円の控除が可能です。同額の控除を配偶者特別控除として受けるには、納税者本人の所得が900万円以下で配偶者の所得が95万円以下であることが条件となります。この条件以降、配偶者特別控除は納税者本人の所得と配偶者の所得が多くなるにつれ減っていきます。
[注5]国税庁「No.1191 配偶者控除」(令和4年4月1日現在)
[注6]国税庁「No.1195 配偶者特別控除」(令和4年4月1日現在)
配偶者控除を受ける際の注意点〜配偶者の年収〜

配偶者控除を受けるには配偶者の年収が条件となりますが、年収によっては税金や社会保険料が発生します。
年収103万円の壁
配偶者の所得がすべて給与の場合、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は年間の給与が162万5,000円までであれば、55万円控除されます。そのため、配偶者の給与収入が103万円以下であれば55万円が控除されて所得が48万円になり、配偶者控除を受けられます[注7]。
[注7]国税庁「給与所得控除」
年収106万円と130万円以上の壁
給与収入が130万円を超えると、正規雇用、非正規雇用に関わらずすべての人が社会保険に加入しなければなりません。そのため、配偶者の扶養から外れて勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険、国民年金に入る必要があります。
また、2022年10月より給与収入が106万円を超える場合、一定の条件を満たしていれば社会保険への加入が必須となりました。[注8]
● 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
● 月額賃金が8.8万円以上
● 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
● 学生ではない
● 従業員数101人以上の勤め先
勤め先の従業員数についての条件は、2024年10月から従業員数51人以上に変更される予定です。
扶養を外れて社会保険に加入した場合、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担が発生します。例えば以下の条件で試算してみましょう。
● 神奈川県在住
● 40歳未満
● 年収131万円(標準報酬月額11万円)
| 全額 | 自己負担額 | 年間自己負担額 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 (標準報酬月額×健康保険料率) |
1万835円 | 5,417円 | 6万5,004円 |
| 厚生年金保険料 (標準報酬月額×厚生年金保険料率) |
2万130円 | 1万65円 | 12万780円 |
このように社会保険の加入によって扶養を外れたことで、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担が増えてしまいます[注9]。
[注8]厚生労働省「パート・アルバイトのみなさま」
[注9]全国健康保険協会「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
年収150万円の壁
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除で最大38万円を受けられるどうかの壁です。配偶者特別控除で最大38万円を受けるには、配偶者の合計所得が95万円までであることが条件です。この95万円に55万円の給与所得控除を足した額が150万円であることが、年収150万円の壁の由来です。
年収201万円の壁
年収201万円の壁とは、配偶者特別控除が受けられるかどうかの壁です。配偶者特別控除を受けるには、配偶者の合計所得133万円以下であることが条件です。給与所得が201万円の場合、68万3,000円(201万円×30%+8万円)の給与控除が発生します。[注10]この給与控除に133万円を足した金額が201万円になることで、年収201万円の壁と呼ばれています。
[注10]国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和4年4月1日現在)
配偶者控除を受ける方法

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるには、年末調整か確定申告での申告が必要です。
配偶者控除や配偶者特別控除を申請するのは年末調整か確定申告のタイミングです。会社に勤めている場合は年末調整時に申請をします。申請の際は「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入したうえで、会社に提出をしましょう。
個人事業主の場合は確定申告時に申請をします。青色申告、白色申告どちらの場合も、確定申告書第一表にある所得控除「配偶者(特別)控除」に控除額を記入します。次に確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」に氏名、マイナンバー、生年月日を記入します。[注11]
確定申告は原則3月15日までが申告期間となっています。[注12]
[注11]国税庁「令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
[注12]国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
年末調整での申告が漏れてしまったら…?
配偶者控除や配偶者特別控除の申告が漏れてしまった場合、確定申告期間内であれば申請できます。
会社に勤めている場合、翌年1月末の源泉徴収が配布される前であれば再度年末調整を申請できる可能性があります。ですが、期限までの時間が短いため、源泉徴収票をもとに自身で確定申告してもよいでしょう。
申告する際は国税庁のホームページで申告書を入手して、期限内に申告書を提出しましょう。[注13]
[注13]国税庁「確定申告書等作成コーナー」
確定申告の申告期限後
確定申告の申告期限後に配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は、「更正の請求書」を税務署に提出します。「更正の請求書」は申告期限から5年以内までであれば遡って提出可能です。[注14]「更正の請求書」も国税庁のホームページから入手可能です。[注15]
[注14]国税庁「【申告が間違っていた場合】」
[注15]国税庁「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」
まとめ
配偶者の所得と納税者本人の所得によっては、配偶者控除として一定金額の所得控除が納税者に対して認められます。配偶者控除の条件を満たしていない場合であっても、配偶者特別控除を受けられるかもしれません。配偶者控除、配偶者特別控除どちらも配偶者の年収が関係しており、配偶者は年収が増えると扶養を外れて社会保険料を支払う義務が発生することがあります。また、納税者は配偶者特別控除も受けられない可能性があります。
配偶者控除や配偶者特別控除は年末調整か確定申告時に申請可能です。申請の際は漏れがないように注意して、期限内に提出するようにしましょう。
※税法上のお取り扱いについては、2022年10月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取り扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。